RANKING
まだ記事がありません
創業・創立・設立の違いを徹底解説!知らないと損する使い分けのポイント
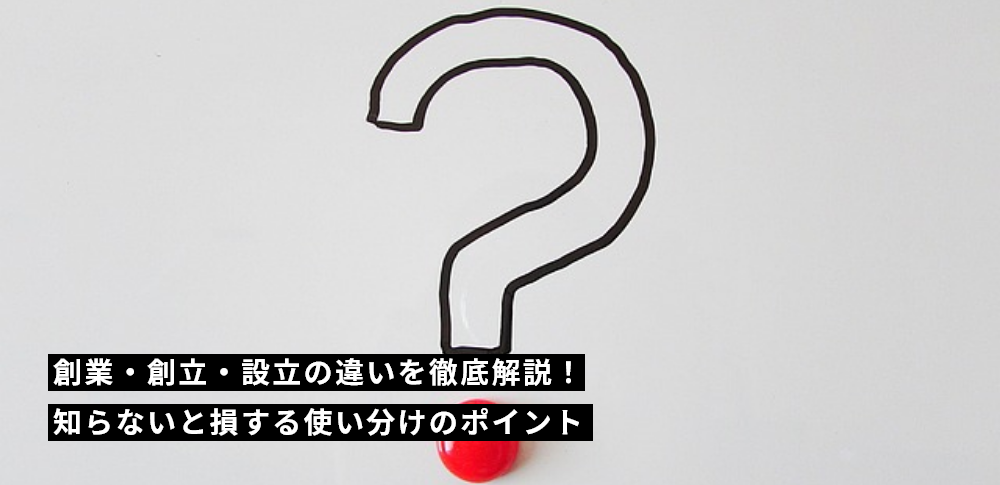
「創業」「創立」「設立」など、似たような言葉が多くて使い分けに迷ったことはありませんか?「創業と設立ってどう違うの?」「どんな場面でどの言葉を使えばいいの?」そんな疑問や悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、それぞれの意味や使い分けのポイントをわかりやすく解説します。これを読めば、創業・創立・設立の違いを自信を持って説明できるようになるでしょう。
目次
創業・創立・設立の定義

創業・創立・設立の3つの言葉は、会社のスタートに関わる用語ですが、それぞれに異なる意味があります。ここでは、それぞれの意味を詳しく解説します。
創業とは
創業とは、新しい事業やビジネスを始めることを指します。
法人格の有無に関係なく、事業を開始した時点から創業とみなされます。
例えば、個人事業主としての活動や法人登記前の準備期間で行う資金調達や事業計画の策定、原材料の仕入れ、不動産の取得なども創業に含まれます。
創立とは
創立とは、組織や機関を初めて立ち上げて事業を開始することを指します。
会社に限らず、学校や団体なども創立に該当し、法人登記や開業届は必要ありません。
創業と混同されがちですが、創立は組織や機関があることが前提です。
したがって、組織を持たない個人事業主の場合は、創立とは言いません。また、既存の会社から子会社を設立したり新しい事業を始めたりする場合も創立とは言いません。
組織を伴う新しいスタートを指すのが創立だと覚えておきましょう。
設立とは
設立とは、会社や法人を公式に登記することを指し、創業や創立とは異なるプロセスを経ます。
設立には法律で定められた手続きが必要で、まず定款を作成し、株主の確定(株式会社の場合)や会社財産の形成、取締役の選任などが行われます。その後、公証人の認証を受けて登記申請を行い、法人として正式に設立されます。
設立日には登記申請を行った日が記録され、法的に確定されるのが特徴です。個人事業主が法人化する場合や、会社が新たに子会社を設立する場合も同様に登記が必要で、その都度設立と呼ばれます。
創業と設立の日付に差があっても問題はなく、設立はあくまで法的手続き上のスタートを示す言葉です。
会社や法人において重要なのは「設立」

会社や法人にとって、法的に最も重要なのは設立日です。
創業日は法的な意味を持ちませんが、設立日は会社が正式に法人格を取得し、社会的に認められる日となります。
設立日は、法務局に設立登記の書類を提出した日を指します。登記完了日と混同されやすいので注意が必要です。
申請方法によって設立日は異なり、窓口申請の場合は提出日、郵送申請では法務局に書類が届いた日、オンライン申請ではデータが受理された日が設立日となります。また、法務局は年末年始や土日・祝日は休みのため、設立日を指定する場合は平日の8:30~17:15の間に手続きを行いましょう。日付にこだわりたい場合は、窓口申請が確実です。
創業・創立・設立の使い分け
創業・創立・設立の違いや定義を理解したうえで、次に気になるのはそれぞれの使い分け方でしょう。
特に、日常生活やビジネスシーンではどの言葉を使えばいいのか、迷うことも多いのではないでしょうか。
ここでは、創業・創立・設立の適切な使い方を具体的に紹介します。
初めて立ち上げた会社の場合:創立・設立
新しく会社を立ち上げる際には、創立と設立の両方が使われます。
厳密に言うと、会社が登記を行った時点で設立となりますが、広い意味で創立と表現しても問題ありません。
例えば、知人が新しく会社を始めた場合は創立または設立という言葉が適しています。
ただし、すでに1つの会社を持っていて、2社目を立ち上げる場合は設立が正しい使い方です。
創立はあくまで初めて組織や機関を立ち上げる場合に使われるため、既存の企業が新たな会社を作る際には設立と覚えておきましょう。
歴史をアピールする場合:創業・創立
会社の長い歴史を強調したい場合には、創業や創立という言葉が適しています。
特に、創業が数百年前であっても、法人としての設立は昭和以降というケースが多くあります。そのため、老舗企業は創業年や創立年をアピールポイントとして活用し、歴史の長さを強みとして伝えることが一般的です。
創業・創立・設立と混同される言葉
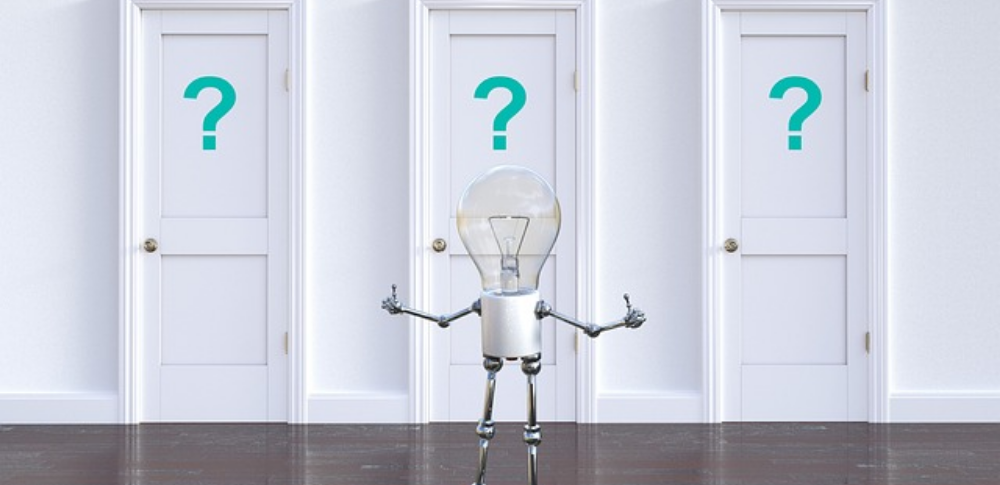
創業・創立・設立と混同されやすい言葉に起業・開業・独立があります。
これらも事業を始めることを指す言葉ですが、意味合いや使い方が異なります。ここでは、起業・開業・独立の意味を解説します。それぞれの違いを理解することで、より正確な表現を使えるようになるでしょう。
開業とは
開業とは、新しく事業を始めることを指し、特に個人事業主が事業を始める際に使われます。開業は会社設立ではなく、個人の事業やお店を新しく始める場合に用いられます。
会社を設立する創業と似ていますが、開業は事業やお店をスタートする場面で使われるのが特徴です。
そのため、事業を開始するタイミングと法人を設立する時期が異なることも多く、開業と創業は必ずしも同時ではありません。
独立とは
独立は一般的に、会社を退職して自分一人で事業を始める際に使われます。
ほかの言葉が事業を始めることに焦点を当てているのに対し、独立は必ずしも事業開始を意味しません。
独立は、同じ職種や業界で独り立ちする際に使われます。
そのため、会社を辞めて全く新しい分野に挑戦する場合や、未経験の状態から事業を起こす場合には、起業という言葉が適しています。
起業とは
起業とは、新たに事業を始めることを指します。
意味としては創業とほぼ同じですが、使われ方が少し異なります。
創業が過去の出来事を指すのに対して、起業はこれから事業を始めるといった未来を見据えた場面で使われることが多い傾向にあります。
特にベンチャー企業を立ち上げる際は、起業という言葉にチャレンジや挑戦といったニュアンスが含まれる場合もあります。
よって、新しいビジネスに挑む際の前向きな姿勢を表すのが起業です。
周年ロゴの制作なら「years」にお任せください!
周年ロゴの制作を考えている方は、周年ロゴ専門サービスの「years」にご相談ください。
周年ロゴの重要性を深く理解し、大切な記念日を彩る高品質なデザインを提供させていただきます。プロのデザイナーによる丁寧なヒアリングを通して、貴社のコンセプトやメッセージをしっかりと反映させたロゴを提案させていただきます。
まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。
CHECK!
関連記事
-

中学校の周年行事におすすめの企画と記念品のアイデアを紹介!
中学校の周年行事の企画や記念品選びに悩んでいませんか?参加者全員が楽しめるユニークなイベントや、心
-
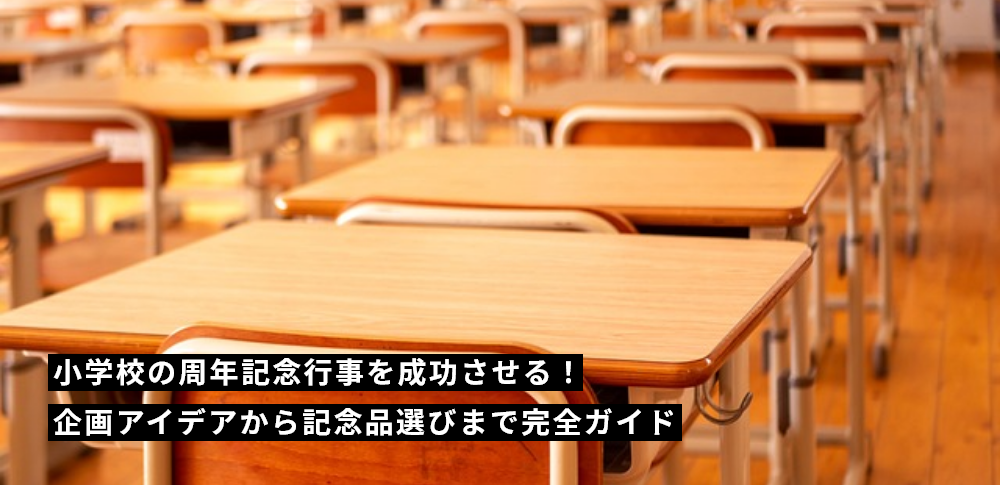
小学校の周年記念行事を成功させる!企画アイデアから記念品選びまで完全ガイド
「小学校の周年記念行事、どんな内容にすれば成功するだろう?」「企画を考えるのが初めてで不安…」「記
-
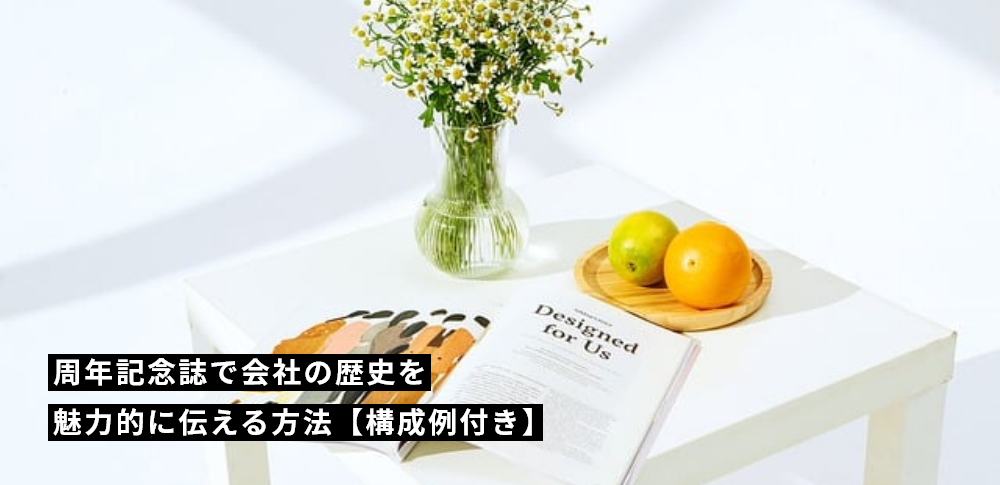
周年記念誌で会社の歴史を魅力的に伝える方法【構成例付き】
会社の周年記念誌を制作するにあたり、「会社の歴史をただの年表にせず、読み手の心に響くものにしたい」
-

初心者でも大丈夫!周年祭のイベントを成功に導くポイントと企画アイデア
周年祭のイベントを任されたけれど、「初心者でもうまく企画できるのだろうか?」「どんなアイデアを出せ
-
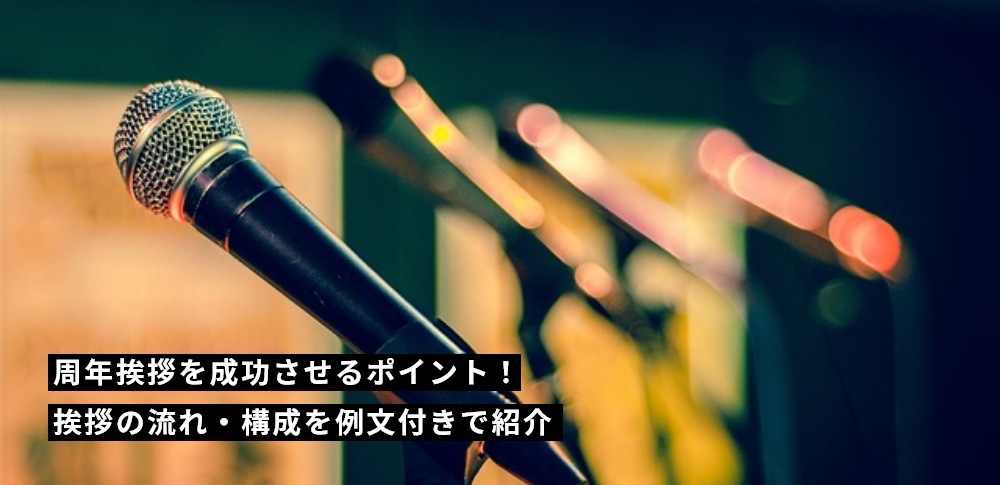
周年挨拶を成功させるポイント!挨拶の流れ・構成を例文付きで紹介
「周年挨拶で何を話せばいいのかわからない」「どうしたら感謝の気持ちをしっかり伝えられるだろう?」こ
-
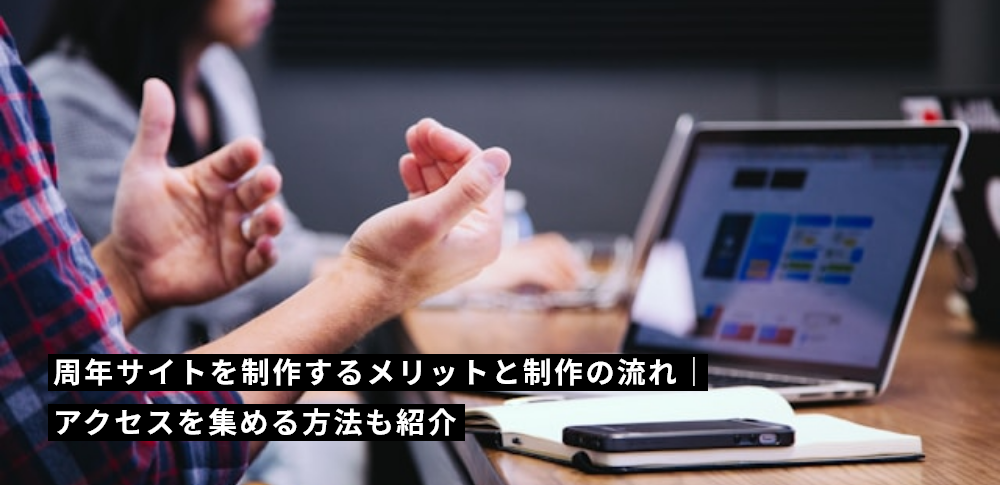
周年サイトを制作するメリットと制作の流れ|アクセスを集める方法も紹介
周年サイトの制作を検討している方のなかには、「周年サイトを作るメリットは?」「制作の手間や費用が気
-

飲食店の周年祝いに贈るべきもの&避けるべきもの|贈り物の相場と贈るタイミングも紹介
「飲食店の周年祝い、何を贈れば喜ばれる?」「失礼に当たらないプレゼントってどんなもの?」と悩んでい
-
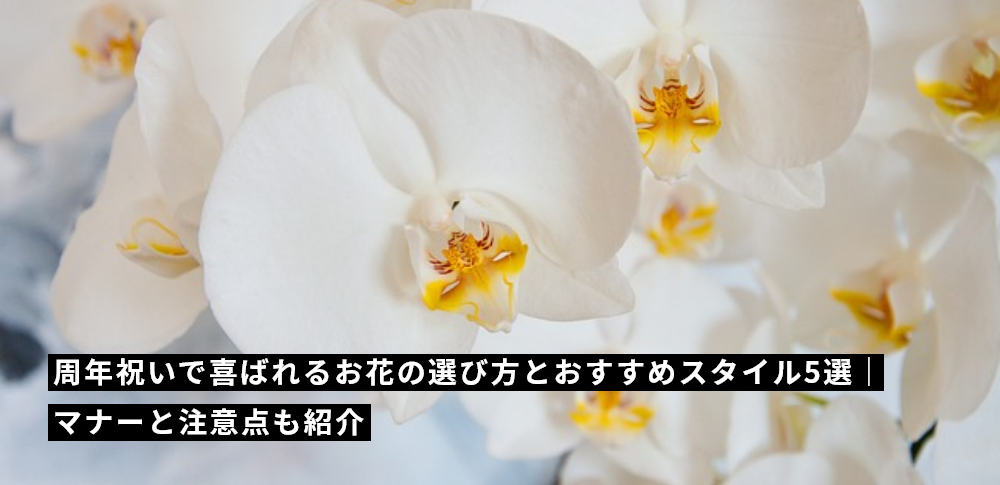
周年祝いで喜ばれるお花の選び方とおすすめスタイル5選|マナーと注意点も紹介
「周年祝いに何を贈れば良いのかわからない…」「相手に喜んでもらえるお花を選びたいけれど、どんな種類
-

ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年!記念イベントやグッズ情報を見てみよう
ウォルト・ディズニー・カンパニーが2023年に創立100周年を迎え、 「どんな記念イベントが開催さ
-
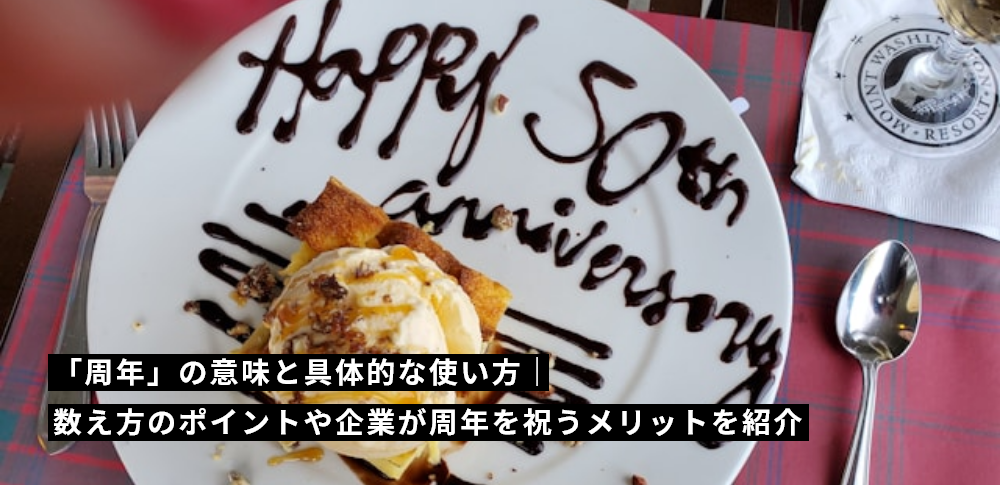
「周年」の意味と具体的な使い方|数え方のポイントや企業が周年を祝うメリットを紹介
「周年ってどう数えるのが正しいの?」「企業が周年を祝うのにはどんな意味があるのだろう?」 など、


