RANKING
まだ記事がありません
周年史とは?社史・記念史との違いと制作するメリット

周年史を作りたいけれど、「社史や記念史との違いがわからない」「制作するメリットって何だろう?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
周年史を制作すると、ブランドイメージの向上や社員の愛社精神の向上などのメリットがあります。本記事では、社史・記念史との違いや制作の流れをわかりやすく解説します。
目次
周年史とは?社史・記念史との違い
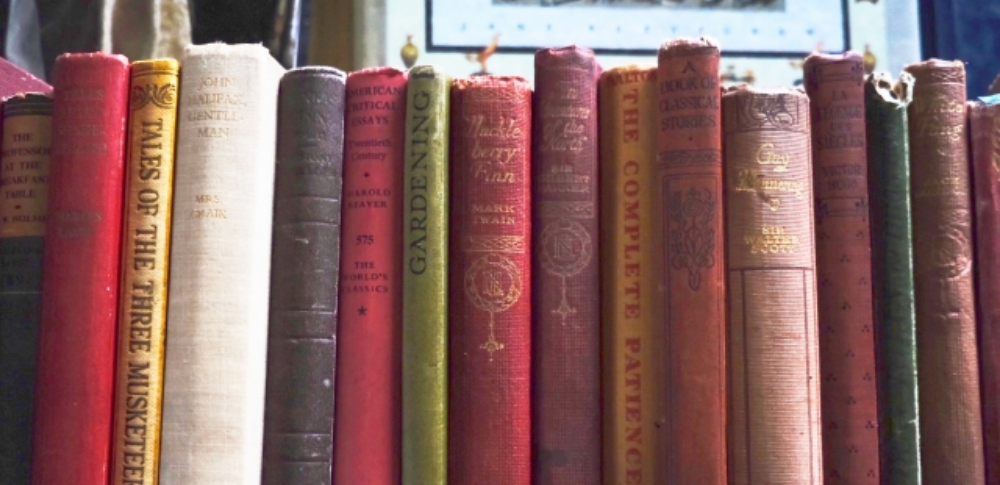
「周年史」「社史」「記念誌」の、それぞれの違いがわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、明確な線引きがあるわけではなく、使い方によっては重なる部分があります。ここでは、それぞれの特徴を簡単に解説します。
周年史とは
周年史(年史)は、企業や学校法人、市町村など、幅広い団体で使用できる言葉です。
通常、○○年史や○○周年史といった形で、特定の年を記念して発行されることが多く、その年までの歴史を振り返る内容となっています。
内容や目的は社史と共通しており、どちらも歴史をまとめた印刷物です。社史は企業に限定される言葉であるのに対し、周年史は労働組合や公共団体など、幅広い団体に使われます。
社史とは
社史とは、企業の歴史を内外の資料にもとづき、客観的にまとめた出版物です。
周年史と異なり、発刊のタイミングは特定の周年に限定されません。上場や社長交代などの節目にも発刊される場合があります。
社史制作するおもな目的は、企業のこれまでの歴史を記録し、後世に伝えることです。
なお、社史にはいくつかの形式があり、それぞれに特徴があります。
| 形式 | 説明 |
| 正史 | 創業前史から発刊時点までの全期間を網羅した社史。全体の歴史を正確に記録したもので、「通史」とも呼ばれます。 |
| 略史 | すでに社史を発刊している場合、その後の歴史を中心にまとめたもの。前の歴史をダイジェストで扱うのが特徴です。 |
| 編年史 | 年ごとに歴史を追いながら記録する形式の社史。時系列に沿って記述されます。 |
| 小史 | 特定の出来事や人物に焦点を当ててまとめられた社史。 |
記念史とは
記念誌とは、周年に限らず、新築や受賞など、特定の出来事を記念して発刊される印刷物です。
記念のお祝いや感謝の気持ちの表現に重きが置かれており、内容や構成は比較的自由です。例えば、著名人との対談や写真中心の構成、寄せ書き形式など、多様な形態が見られます。社史や周年史が企業や団体の歴史を記録することを目的としているのに対し、記念誌は特定の出来事を祝う意図が強く、歴史記述は必須ではありません。
例えば、創業50周年を迎える際、歴史の記録が目的なら「社史」や「周年史」、関係者への感謝を伝えることが目的なら「記念誌」が適しています。
周年史を制作するメリット

周年史は、単なる記録に留まらず、社内外へのコミュニケーションツールとしても重要な役割を果たします。ここでは、周年史を作成するメリットを紹介します。
ブランドイメージが向上する
周年史の制作は、企業のブランディング向上につながります。
普段は伝えにくい企業の信念や実績を一冊にまとめると、企業の存在意義を効果的にアピールできます。
社内の意思統一やスタッフの教育に役立つだけでなく、取引先の理解を深め、新たな人材の採用や取引先開拓のツールとしても活用可能です。
社員の愛社精神が高まる
周年史を制作すると、企業の過去を振り返り、未来のビジョンを考えるきっかけとなります。
特に、創業者のメッセージや若手社員のインタビューなど、社員参加型のコンテンツを取り入れると、社員が企業の理念や価値観を再確認できます。また、編纂の過程そのものが、社員同士のつながりを深め、一体感を高める効果もあります。
採用ツールにも活用できる
周年史を採用説明会で配布したり面接時に学生に手渡ししたりすると、Webサイトだけでは伝えきれない企業の魅力を伝えられます。
周年史を配布する際は、持ち運びがしやすい文庫型やA4サイズの小冊子型にするとよいでしょう。
【5ステップ】周年史を制作する具体的な流れ

制作期間は、規模や内容により異なりますが、企業の歴史を網羅する社史の場合は完成までに3年ほどかかる場合もあります。充実した内容にするためには、少なくとも1年の準備期間を見込むとよいでしょう。周年史の制作過程は大きく5つのステップに分けられます。
ステップ1.プロジェクトチームの発足
周年史の制作が決まったら、まず社内で周年史編纂のプロジェクトチームを立ち上げましょう。広報課や秘書課、社歴の長い社員や愛社精神の強い若手社員など、適性を考慮して幅広くメンバーを集めます。チーム長には、決定権を持つ人が適任です。また、企業トップの意向を反映するため、必要に応じて経営層の参加も求めましょう。
周年史の制作には専門的な編集スキルが必要なため、デザインやライティングは外部に依頼するのが一般的です。周年史制作をサポートしてもらえる出版社に依頼すれば、効率的に進められます。
ステップ2.出版社や制作会社の選定
プロジェクトチームを編成したら、周年史を制作する目的やコンセプト、発行時期、予算を決め、早めにパートナーとなる出版社や制作会社を選定します。
出版社や制作会社は、記念誌制作の経験が豊富で、スケジュール管理や進行サポートが充実しているところだと安心です。単に作業を代行する会社ではなく、企業の理念や想いを理解し、伴走してくれるところを選びましょう。
特に、出版や編集のプロがそろい、ライターやデザイナーと連携できる出版社や制作会社を選ぶと、スムーズに作業が進行します。
ステップ3.企画・構成作成
周年史の企画・構成では、制作の目的や読者層、組み込む内容を明確にすることが大切です。周年史を制作するゴールをしっかりと定めると、作成の方向性が定まります。
また、周年史は節目の年に発刊するため、スケジュールの管理も重要です。ここで無理のない進行計画を立てることが、完成度の高い周年史を作る鍵となります。
周年史制作を得意とする出版社や制作会社のサポートを受けると、企画から構成までスムーズに進められます。
ステップ4.制作を進める
企画・構成が決まったら、実際の制作に進みます。取材や写真撮影、資料集め、原稿・デザインの制作が中心です。
ライターやカメラマンなどの外部クリエイターの協力を得ながら、コンテンツの質を高めていきます。プロのアドバイスをもとに、資料の収集や寄稿文の依頼、インタビュー、デザインの作成を進めていきましょう。
ステップ5.校正・製本
ライターがまとめた原稿、そして出版社が提案してくるデザインをチェックします。出版物は一度印刷されてしまうと修正ができないので、ニュアンスや表記の誤りなどを、複数人でチェックします。校正やデザインが終わり次第、原稿を印刷所へ入稿します。
周年ロゴの制作なら「years」にお任せください!
周年を迎える特別な瞬間に、オリジナルのロゴを制作しませんか?
周年ロゴは、単なるデザインにとどまらず、これまでの歩みや感謝の気持ち、未来への希望を込めたシンボルです。イベントやキャンペーンに活用できるだけでなく、記念品やWebサイト、広告にも幅広く展開可能です。
「years」では、丁寧なヒアリングを行い、ご要望に合わせたオリジナルのロゴを制作いたします。
まずはちょっとした質問やご相談からでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。
CHECK!
関連記事
-

飲食店の周年祝いに贈るべきもの&避けるべきもの|贈り物の相場と贈るタイミングも紹介
「飲食店の周年祝い、何を贈れば喜ばれる?」「失礼に当たらないプレゼントってどんなもの?」と悩んでい
-
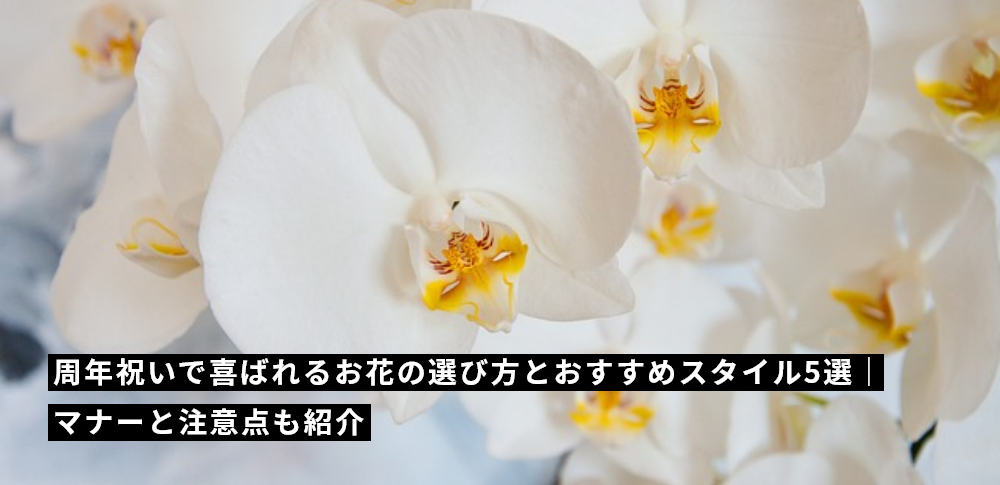
周年祝いで喜ばれるお花の選び方とおすすめスタイル5選|マナーと注意点も紹介
「周年祝いに何を贈れば良いのかわからない…」「相手に喜んでもらえるお花を選びたいけれど、どんな種類
-

ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年!記念イベントやグッズ情報を見てみよう
ウォルト・ディズニー・カンパニーが2023年に創立100周年を迎え、 「どんな記念イベントが開催さ
-
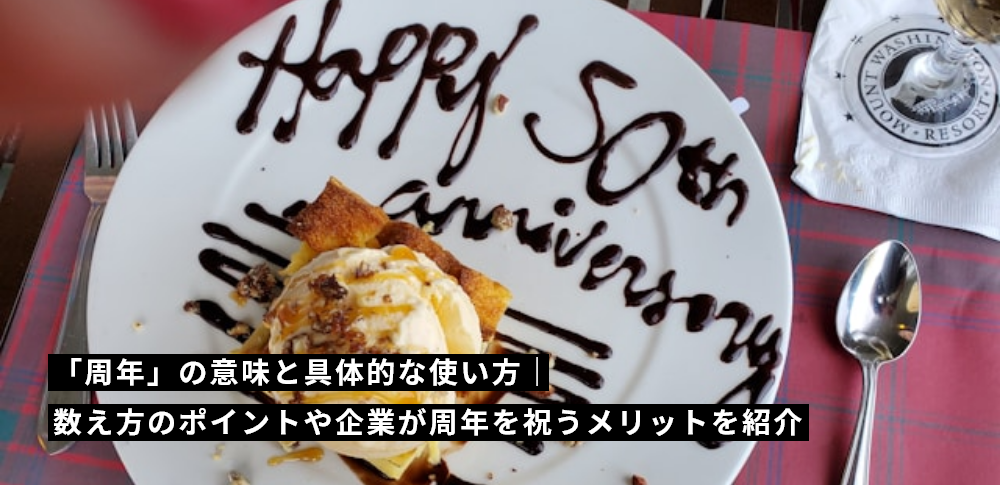
「周年」の意味と具体的な使い方|数え方のポイントや企業が周年を祝うメリットを紹介
「周年ってどう数えるのが正しいの?」「企業が周年を祝うのにはどんな意味があるのだろう?」 など、
-

周年ポスターの作り方|初心者でもわかる基本とデザインのポイント
周年ポスターを作りたいけれど、「どこから手をつければいいのかわからない」 「デザインセンスがない
-
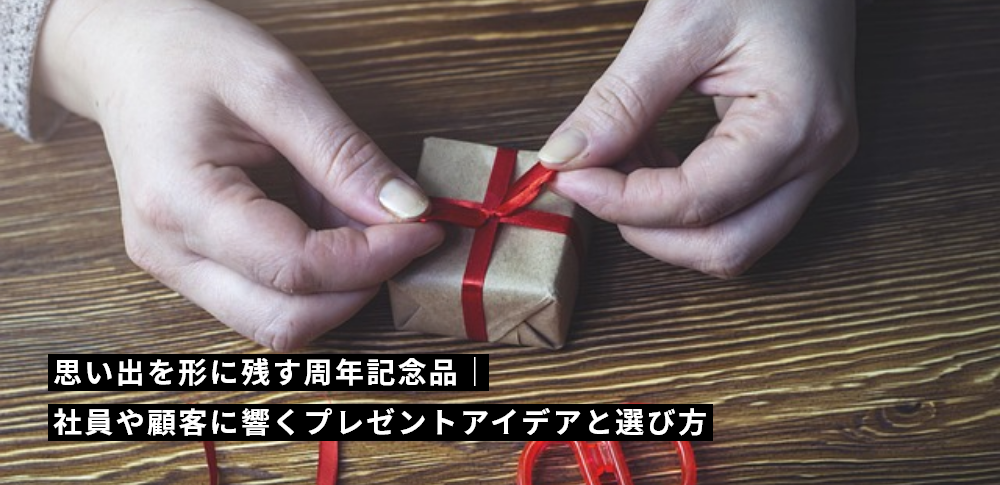
思い出を形に残す周年記念品|社員や顧客に響くプレゼントアイデアと選び方
記念すべき周年を迎えるにあたり、「何か特別な記念品を用意したいけれど、どんなものが喜ばれるだろう?
-
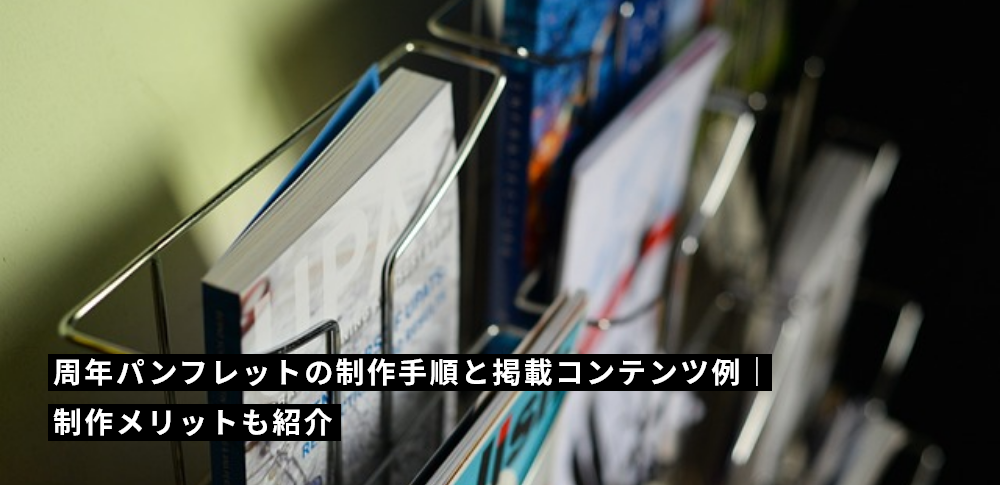
周年パンフレットの制作手順と掲載コンテンツ例|制作メリットも紹介
周年パンフレットを作りたいけれど、「どこから手をつければいいのかわからない」「どんな内容を掲載すれ
-

周年プロモーションを成功させよう!計画と実施、周知のポイントを解説
周年プロモーションを計画しなければならないけれど、 「どこから手をつければいいのかわからない」
-
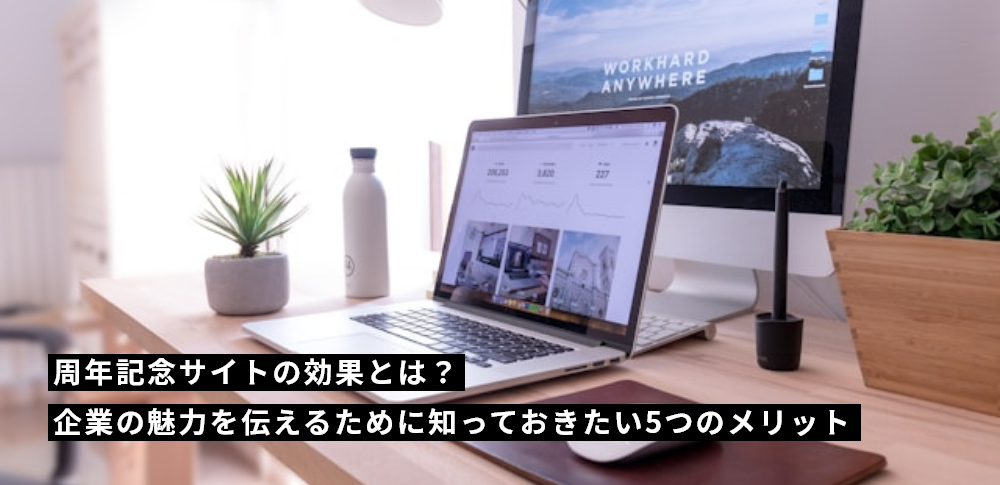
周年記念サイトの効果とは?企業の魅力を伝えるために知っておきたい5つのメリット
「周年記念サイトを作るべきかどうか悩んでいる」「具体的なメリットがわからず、なかなか踏み切れない」
-

周年フェアの成功事例7選|成功させるポイントとプレゼントに最適なノベルティを紹介
周年フェアを企画中の皆さんは、「印象に残るノベルティって何を選べばいいの?」 「他の企業の成功事


